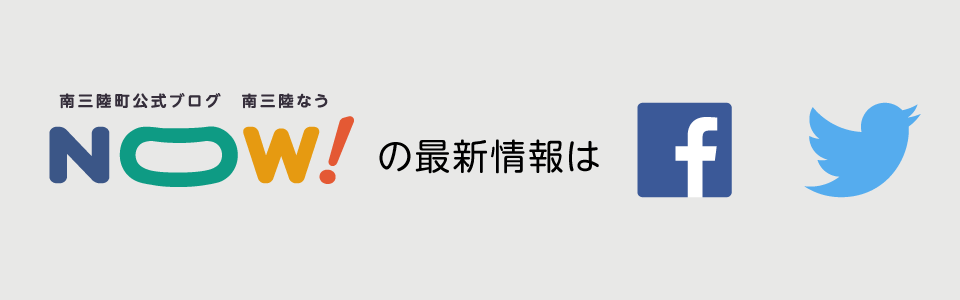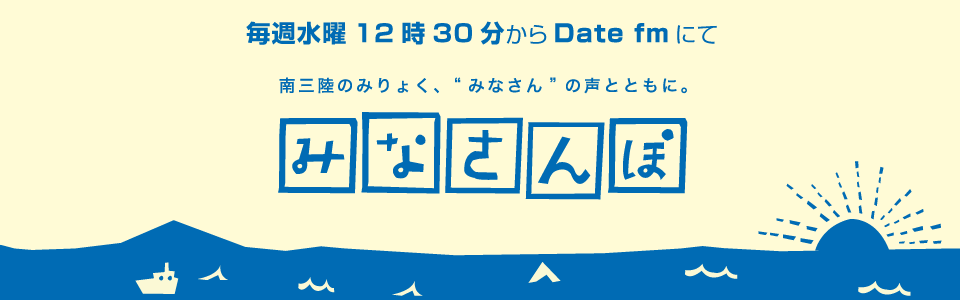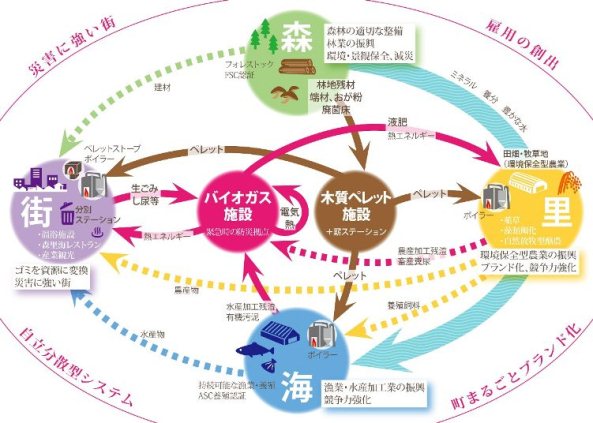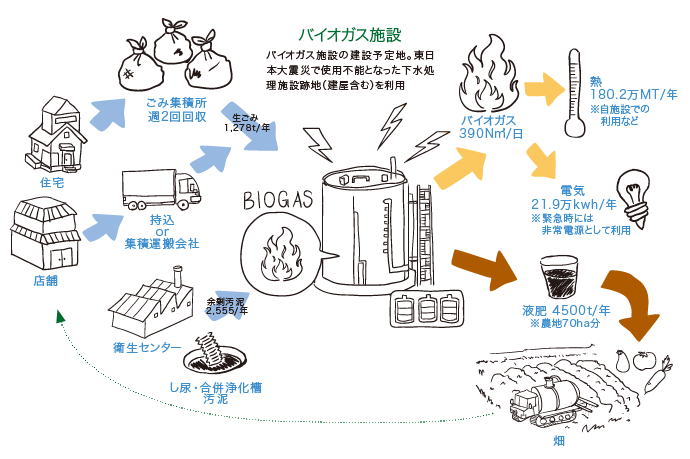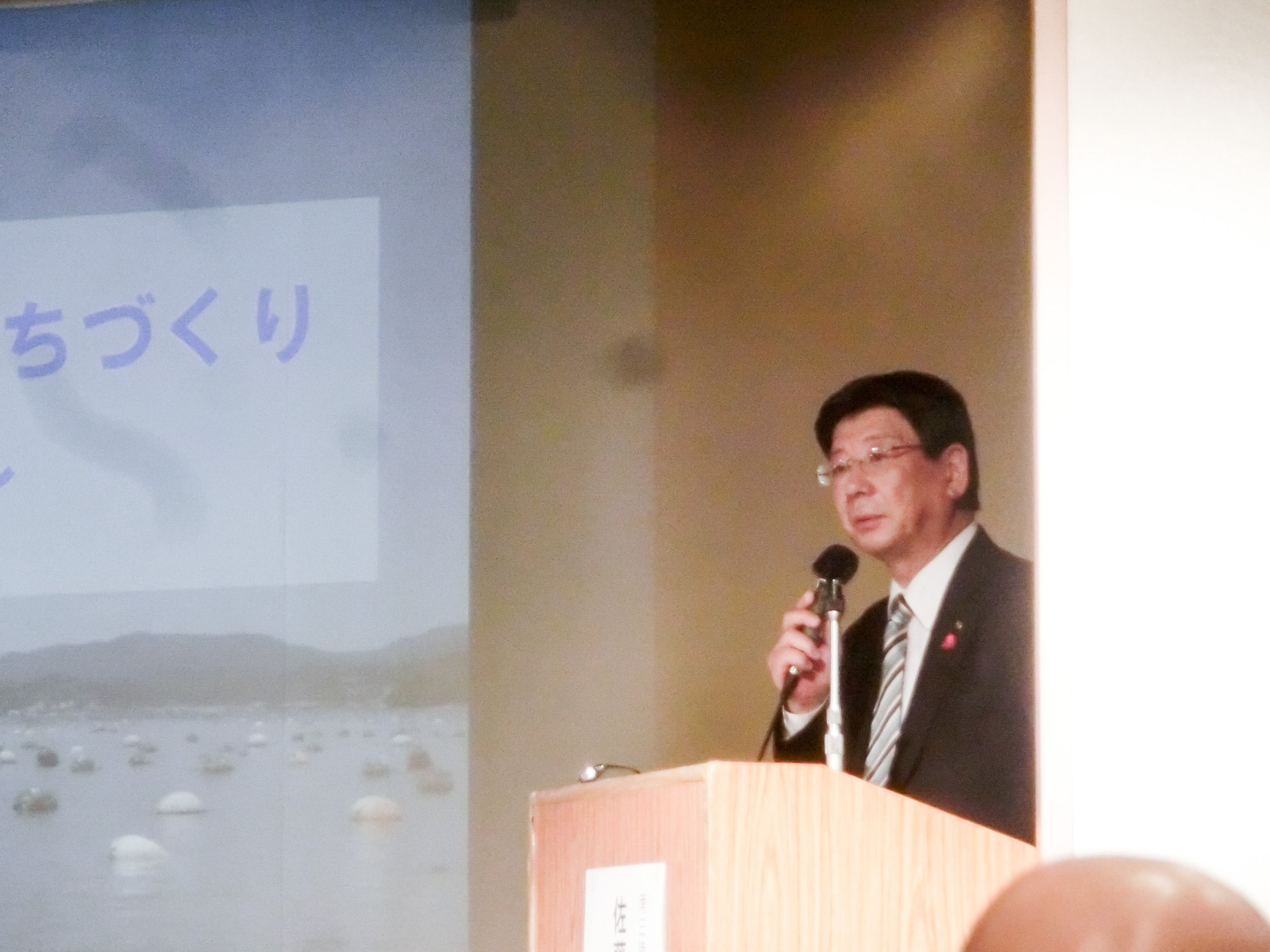歌津平成の森敷地内にある集会所『南三陸歌津迎賓館「鍵」』で音楽イベントが開催されました。イベントの様子とともに、前方後円墳の形をした、この不思議な竪穴式集会所についてご紹介します。
南三陸町歌津地域の多目的総合施設「平成の森」
歌津の高台に位置する「平成の森」は、アリーナ・トレーニングルーム・宿泊施設・レストランなどなど、季節を問わず様々な用途で使える、多目的総合施設です。
敷地内には町役場歌津支所や図書館なども併設されているほか、ナイター施設を備えた野球場では毎年、楽天イーグルスのイースタン公式戦も開催されています。日帰り可能な温浴施設も備わっており、観光やボランティアでお越しの際もご利用いただけます。
東日本大震災時には避難所として機能し、現在でも大規模な仮設住宅が残っている場所でもあります。

歌津迎賓館「鍵」
平成の森野球場のはじっこに、集会所として建設されたのが『南三陸歌津迎賓館「鍵」』です。
見慣れぬその形は、さながら「前方後円墳」のよう。そして、入り口から地中へと掘りこまれたそのつくりはまさに「竪穴式住居」の様相です。小学校の教科書のおさらいができますね。覚えていますか?
立派な木の柱に土壁、中央には囲炉裏を構え、壁には絵師・香川大介さんによる阿吽の獅子の絵が描かれます。地元伊里前の契約会が伝える獅子舞を描いたものだそう。
この迎賓館「鍵」は、歌津地区の震災復興のシンボルとして、たくさんの方々のご支援やボランティアにより2012年5月に完成しました。以後、地域の方の集会所として様々な用途で活用されています。

復興応援グループ「チーム日光」
震災直後、避難所や仮設住宅への移転によりコミュニティが分断される中、地域の人々が団結する必要がある、そのためには皆が集まる共有の場が必要である、という地元の方々の強い思いを形にするべく、「鍵」を建設するプロジェクトが立ち上がりました。
プロジェクトの中核グループは、栃木県の方を中心に結成された復興応援グループ「チーム日光」。震災直後に立ち上がり、石巻市や南三陸町を中心にご活躍されてきました。「鍵」はチーム日光のみなさんにより、2011年から制作されました。
たくさんの募金や作業ボランティアの方々によって、わずか1年ほどで完成し、地元の方々へ引き渡されました。
その独特な形状や建築方式には、シンボリックかつ低予算であり、また日本古来の伝統的な作りである竪穴式の建築に加え、寄合の場としてふさわしい円形を取り入れた前方後円墳の形状、また間伐材の利用や太陽光発電の利用などの自然環境への配慮もなされています。
日本の住居の「原点」に立ち返り、原点に返ってもう一度ここから再出発しよう、という想いが込められているそうです。

keys session vol.1
2016年4月24日に「鍵」で音楽やアートを中心にしたイベントが開催されました。題して「keys session vol.1」。
地元の方々を中心に、楽器演奏・歌のほか、DJや詩の朗読・ライブペインティング、さらには来場者誰でも参加OKの即興演奏など、多岐にわたる方々の出演や催しがありました。
一見怪しげな雰囲気ながら、豊かな自然に囲まれた歌津平成の森の立地と、丸太や土壁でつくられた「鍵」の雰囲気、ライブペインティングで参加される「Kemono gallery」の小野寺達也さんの明かり、そして出演者の奏でる心地よい音楽に、とても心地良い空気が流れます。

「TATEHAMA DIAL HOUSE」千葉和人さん
主催されるのは地元館浜出身の千葉和人さん。音楽を愛し、被災しながらもプライベート音楽スタジオ「TATEHAMA DIAL HOUSE」を建て、地域の方々と音楽活動を楽しみます。
「この町で楽しく暮らしていきたい、そのためのきっかけにしたい」と今回のイベント開催に踏み切ったそう。会場として「鍵」を選択したのには、音楽という“ものづくり”をおこなう千葉さんの精神と、DIY精神の極みとも言うべきこの竪穴式集会所に、共鳴するものを感じたからといいます。千葉さんが運営する「TATEHAMA DIAL HOUSE」も、「楽しい場所が無ければ自分でつくればいい」というまさにDIY精神によるもの。
「町内は若者が楽しめるスペースが少ないので、希望が持てる場所になれば、うれしいですね」と、このイベントにかける想いを語ってくださいました。

楽しい場所が無ければつくればいい
「ものづくりを突きつめる者にとって、あの建物で表現ができることはとても贅沢でありがたいことだと思います。その価値を発信していくとともに、あの場所に関わった方々の思いをつないでいきたいです。そしてその輪が広がっていけばいいなと思います。今後もあの場所で手作りのイベントを継続していきたいと思います」と、今後の抱負についても語ってくださった千葉さん。
これまで5年間、たくさんの方々のご支援に支えられ復興の歩みを進められた私たち南三陸町民は、決して感謝の思いを忘れはしません。
また今後、ますますの町の復興や発展へ向けてその歩みを止めることなく、これまでご支援いただいたみなさまへ精一杯の恩返しができるよう、楽しく豊かに暮らしていける町としていく責務があります。
「楽しい場所が無ければつくればいい」と町の輝かしい未来へと万進される千葉さんから、復興への希望の光や心強さを感じるイベントでした。