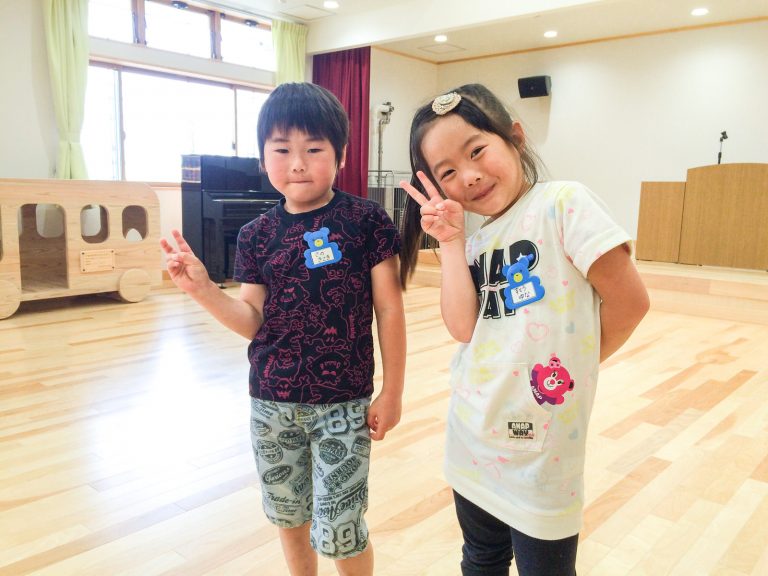「聞いでけさいん町長さん」は、その名の通り、協働のまちづくりを実現するため、町長が地域に出向き、みなさんと建設的な意見交換を実施する機会です。今回「NPO法人びば!!南三陸」が町長を招いたとのことで、取材に伺いました。
「聞いでけさいん町長さん」とは
他の町から南三陸に来た人は、町長と住民の距離の近さに驚くかもしれません。そんな町長と住民の距離の近さを物語る場に伺いました。
「聞いでけさいん町長さん」(訳:聞いてちょうだい、町長さん)は、その名の通り、10名以上の町内団体であれば誰でも町長を招いて、建設的な意見交換ができる制度です。
以前は、「出前トーク」の名前で実施されていましたが、震災後は一時中断していました。今年度より名前もより親しみやすくなって再開し、今回が第一回目の開催となります。

地域住民の集いの場「晴谷驛(はればれー)」
今回、町長を招いたのは、入谷で高齢者のための生きがい作り活動をしている「NPO法人びば!!南三陸」です。「あそびば」、「まなびば」、「むすびば」の3つの楽しい「びば」の機会を創出し、地域住民がいきいきと生活できる手助けをされています。その「NPO法人びば!!南三陸」が管理・運営している施設が、入谷でひときわ目立つ赤と青のスタイリッシュな建物「晴谷驛(はればれー)」です。どちらもネーミングにユーモアのセンスが光ります。
そこに足を踏み入れると、既に多くの紳士淑女の方々が、町長の登場を待っていました。

「写真では見ていたけど、実際に来るのは初めて。こういう機会でもないと来ることもないから、今回は呼んでもらえてありがたい」と町長。
コンテナに囲まれたスペースは、色とりどりのモザイクで彩られていて、まるでスペインの広場のようです。このモザイクアートに使われているのは「エコ平板」というもので、「NPO法人びば!!南三陸」の方々が、日々鋭意製作しているものです。この床も、みなさんで一つ一つ並べて作ったそうです。

他にも、クラフトテープを用いてカゴや小物入れを創る「エコクラフト」や日曜大工、陶芸など、様々な講座が開講されています。特技のある住民が講師となったり、地域外から先生を招いたりしながら、お互いに腕を磨いています。
町長の前で自慢の作品を披露して、住民の方からも笑顔がこぼれました。

その他にも、地域の歴史や文化について学ぶ「地域学び塾」、みんなでバスに乗って町外に足を伸ばす「視察ツアー」など、様々な企画が開催されているそうです。
「歳とると、家にいても一人とか、夫婦二人とかだっちゃ?こうやって通ってくる場所があるっていうのはありがたいよね。ここに来ると毎日が楽しいよ」と住民の方は語ります。世間では60歳以上は「高齢者」とひとくくりにされてしまいますが、人生80年と言われる昨今、60代も70代も、80代だってまだまだ現役です。長年の経験と知恵を持ち合わせ、地域にも精通した大先輩たち。彼らが元気であれば、町全体が元気になることは間違いありません。
町長との建設的な意見交換会
司会を務める代表理事の鈴木清美さんから、今日の町長との対話における3つのテーマが発表されました。

- 震災前にあったシルバー人材センターが今後どうなるのか
- みんなで作っているエコ平板のモニュメントを、復旧後の町で使ってもらいたい
- 今後の高齢者の暮らしがどうなるのか
震災前、南三陸町にはシルバー人材センターがありました。現役を退いた元気なおじいさん、おばあさんたちが、植木の剪定や宛名書き等、様々な仕事を請け負っていました。長年の経験に裏打ちされたまじめな仕事ぶりは高く評価され、町内でも重宝されていました。総会や会員交流会ともなれば、趣味の活動を行う友の会の会員も合わせて100名以上の大宴会が催され、非常に盛り上がっていたそうです。
シルバー人材センターは諸事情で、一旦解散という形になっています。それでもせっかく培ったつながりを絶やさず、震災でコミュニティもばらばらになったからこそ、高齢者がいきいきと活動できる場を作りたいと活動を続けてきたのが、この「NPO法人びば!!南三陸」(前身は「いぶし銀倶楽部」)でした。そして、従来のシルバー人材センターの役割である、働きたい方と作業を頼みたい方をマッチングする機能に加え、住民が交流や趣味の活動に打ち込んで楽しく過ごす手助けをし、それがまた各々の良い仕事につながる…そんな進化版シルバー人材センターの形を「NPO法人びば!!南三陸」は模索しているのです。
「清美くんやさっちゃん(事務局長の西城幸江さん)にはいつも言ってるんだが、シルバー人材センターはぜひとも復活してもらいたい。今こそ、町の様々な層の人が活躍できるシステムが必要だ。どんどんやってくれ!」と町長からは力強い返答がありました。

また、エコ平板モニュメントに関しては、住民のみなさんの手作りのモニュメントに感心しながら「これから復興記念公園もできるし、使える場所はたくさんある。十二分に検討します。デザイン・技術に磨きをかけていてください!」とこれもまた期待のもてる言葉がありました。
顔の見える間柄だからこその対話の場
ところでね、と町長が口を開きました。
「震災から5年経つというけれど、当然ですが私も5歳年をとるんですよね。震災直後の写真と、今の写真を見比べると、老けたなあって・・・。しかし、みなさん、震災前と変わらず、お元気そうでほっとしました」
そう、現役のころは、様々な場面で町を支え、盛り上げてきた先輩方。町民と町長という間柄になる以前から、顔見知りであり同志でもあったみなさんです。
そこからは、一気に和やかな雰囲気に。今年度で住宅地の復旧の目処が経った今だからこそ言える苦労話も飛び出しました。
「町長さんのがんばりも大きかったもんね」大先輩からの言葉に、町長の顔もほころびました。
和やかな対話のなかに、お互いの立場を尊重する思いやりの心が見えました。
今度はあなたのところに町長を呼んでみよう
その後、質疑応答は町長だけでなく、同行していた役場の職員にも及び、約60分の時間はあっという間に過ぎました。終了後に参加者の方に話を伺うと、「町長が公の場で、シルバー人材センターの再建について意欲を示したのはこれが初めて。来てもらってよかった」とおっしゃっていました。今度はあなたの所属する団体、職場、学校でも、町長を呼んでみてはいかがでしょうか?