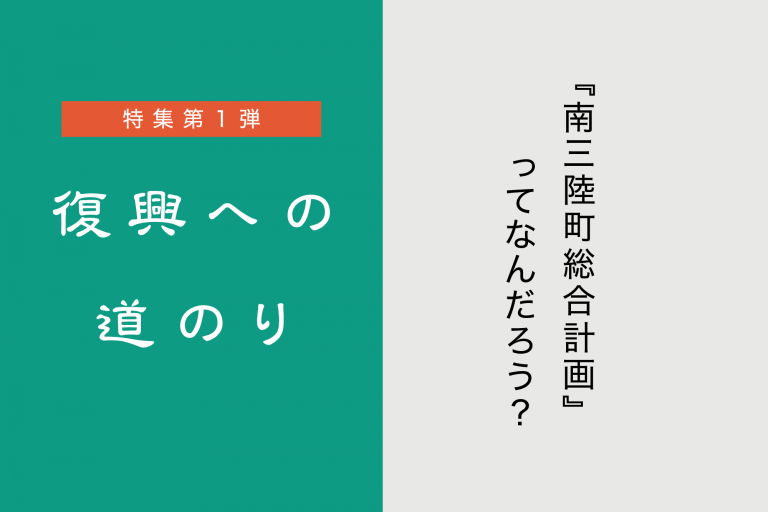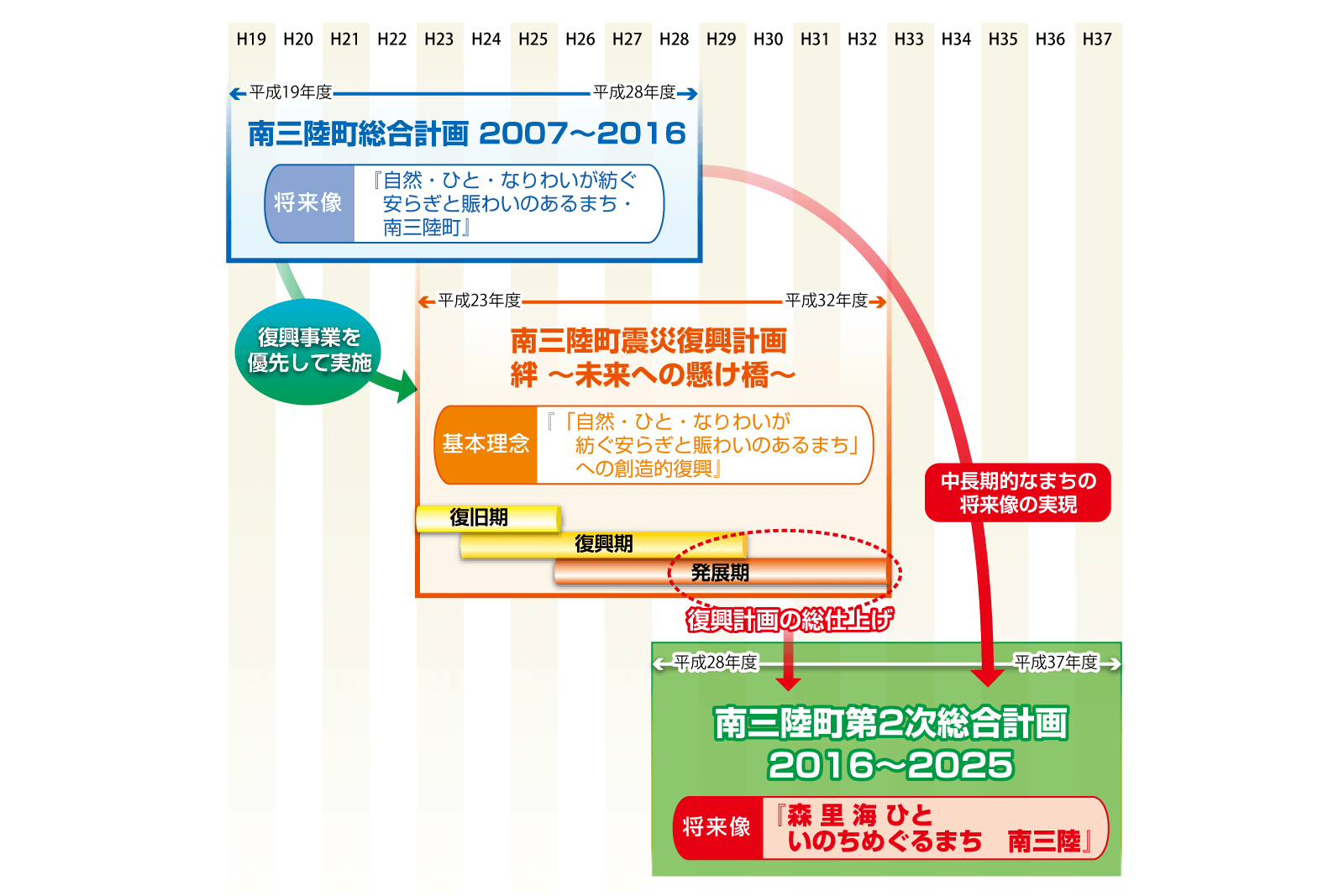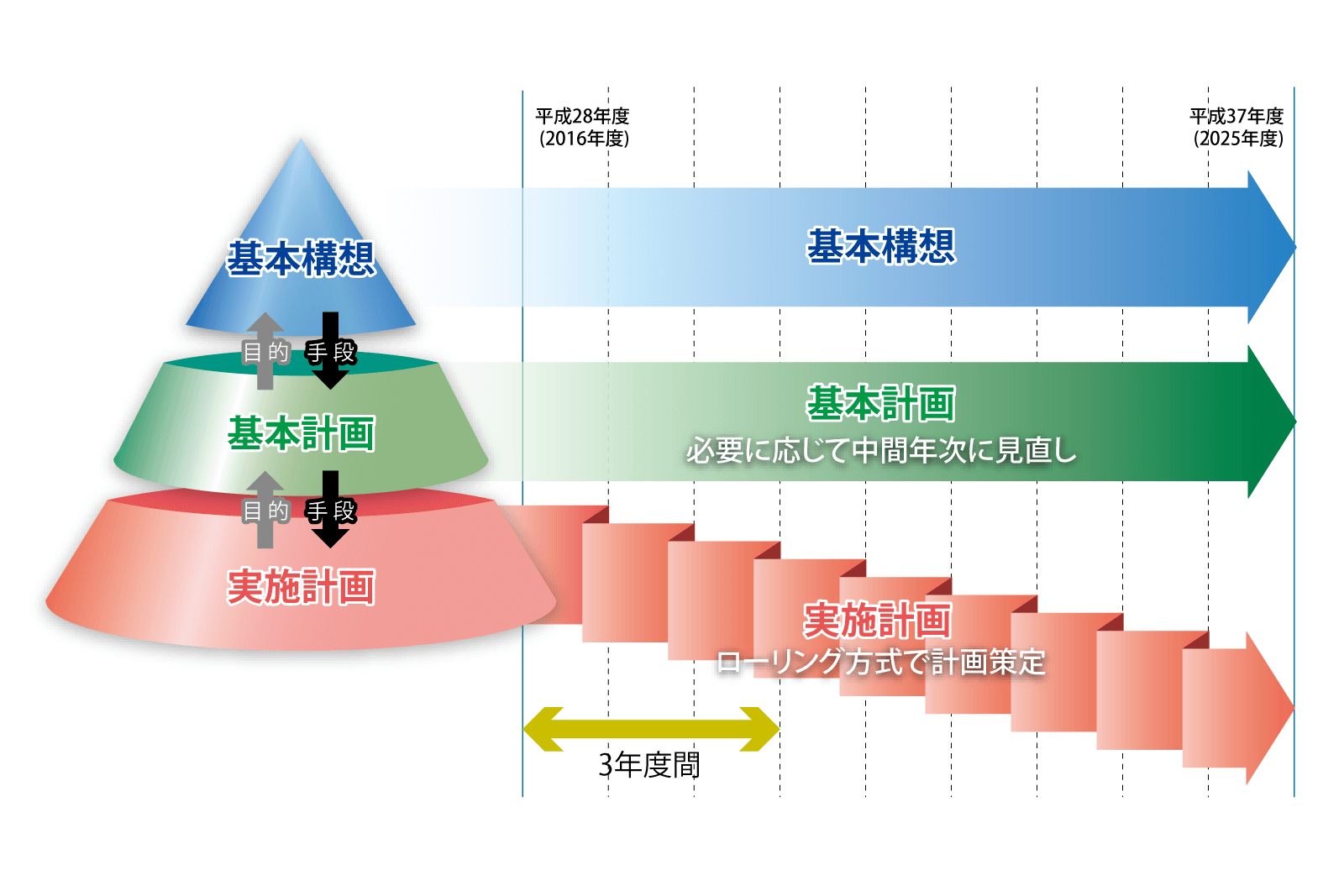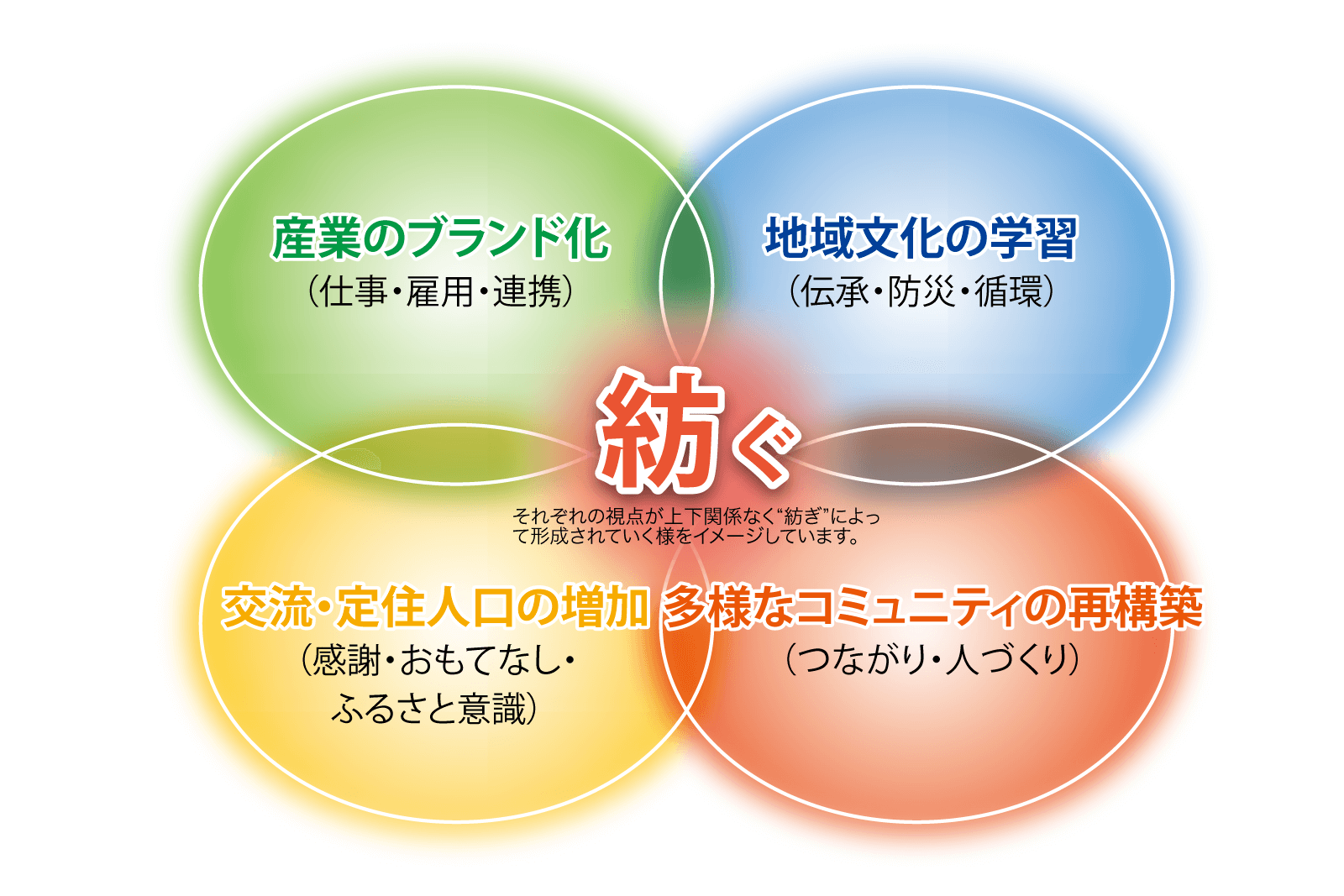東日本大震災以降、15万人以上のボランティアが、「南三陸町災害ボランティアセンター(以下ボラセン)」を通じて南三陸町を訪れました。ボラセンが果たした役割は何だったのか。南三陸町社会福祉協議会 事務局長の猪又隆弘さんにお話を伺いました。
「南三陸町災害ボランティアセンター」は、どのようにして立ち上がったのか
―まずは、南三陸町災害ボランティアセンター(以下「ボラセン」)の東日本大震災発災直後からこれまでを段階的に教えていただきたいと思います。
震災以前から、発災時には地元の行政と社協(社会福祉協議会)がボラセンを立ち上げるという協定を結んでいました。私も何冊ものマニュアルを作ったし、何度も訓練を行ってきました。しかし、3.11の地震による津波は社協の事務所があった「福祉の里」にまで到達し、マニュアルも資材も何もかも流されてしまったのです。
―猪又事務局長も被災されたのですか?
はい、私自身も一週間は志津川高校で避難生活をしていました。そして、山形県社協と大阪府堺市社協の支援を受けて、何とかボラセンを立ち上げたのが3月26日のことです。当時の役場職員は避難所に張り付き、避難所の運営から罹災証明の発行事務まで、とにかく忙しくて手がまわらない状態でした。なんとかして、役場職員を次の業務にひっぱりたいから、とにかく早くボラセンを立ち上げてくれと、当時の総務課長から要請があり、ベイサイドアリーナの敷地内に学校用テントを3つたてて窓口を作ったのが始まりでした。

ボランティアの力を生かす
—3つのテントからボラセンが始まったんですね。初期の活動はどのようなことを行ったのですか?
初期は安否確認や避難所の衣食住に関わることなど、医療以外は全てやりました。4月以降は、徐々にボランティアが入ってきたので、避難所のニーズを把握し、物資の整理やがれき撤去にボランティアをマッチングさせるということを行いました。物資なんか、1日に10トントラックが2台も3台も入ってくるし、ダンボールの中身もバラバラだし、地元の人間だけでさばけるわけないんですね。本当は早いところHP立ち上げて、今必要な物資はこれこれです、ということをやりたかったけど、とてもそんな状況ではありませんでした。そんな時に、初期に入ってきたボランティア3人を、雇用という形で本部付けにしたんです。
―ボラセンがボランティアを雇うというのは、もちろん当初は想定していなかったことですよね?
おそらく、日本初の事例でしょうね。要は、地元の人間が持っていないスキルを、彼らは持っているんです。さらに、被災者が支援者になるということは、その人に大きな負担を強いることになります。そこをこの3人は軽減してくれました。
本部は一日中、マスコミ対応やボラセンの仕組み作りでほんろうされるので、現場はその時入ってきたボランティアに任せて、報告だけ受けるようにしました。普通は、本部、マッチング班、資材班…と分かれて30人くらいの組織構成になるのですが、安否確認だけで2ヶ月はかかっているし、電気も水もないところに、人を集められるわけがない。結局、人で回せる仕組みにしました。
彼ら3人は1年間ずっといてくれましたね。その間は私より高い給料を払っていました。専門的なスキルを持っているのだし、こっちにいる間、彼らの地元の生活も担保しなければならないので、当然のことだと思います。さらに、長期のボランティアが20名ほどいました。彼らに現場までの道案内や道具の整備、作業の指示等を一任できたので、事故率は随分減りました。長期とはいえ、彼らはみんな車中泊で、食料も自前だったんです。
—車で寝泊まりして、ボランティアをしてくれたんですね。
南三陸のためにここまでしてくれているのに、これでは上手くないということで、最低限、寝る場所を準備したり、シャワーを整えたり、長期ボランティア向けの炊き出しをセッティングしたりはしましたね。シャワーは、長期のボランティアの人が漁協の水槽なんかを使って手作りしました。見落とされがちですが、ボランティアのためのボランティアというのも必要なのです。

産業支援に踏み切る
—体育館などの避難場所から徐々に仮設住宅に移行していった時期では、どのような活動を行いましたか?
今までやっていなかった「産業支援」に踏み切りました。震災の翌年の3月頃のこと、現場にいて支援を待っているだけじゃ限界があると感じて、東京に出向いていったんですね。「復興支援説明会」という形で場を設けさせてもらって、全国の企業約60社にお集まりいただきました。そして、商店街の方や漁協さんと一緒に町の現状を訴え、こういうわけなので、ご協力を願いますという話をさせていただきました。
ボラセンが旗振りをしてこのような場を設けたのは日本で初めての試みでしょう。踏み切るまでには少し悩みました。役場や商工会がやることで、ボラセンが手を出すべきではないのではと思ったからです。しかし、どこも職員は疲弊している。今注目を集めているうちに少しでも外部とのつながりをつくらなければということで、行きました。
同時に、漁業で言えばわかめの最盛期の手伝いだったり、農業で言えば農地の復旧のための石拾いだったりといった産業分野にもボランティアをマッチングさせていきました。この先の町の復興を考えたときに、産業の復旧は喫緊の課題だと考えたからです。産業のないところに雇用は生まれない。雇用のないところに人は戻ってきませんから。

「企業ボランティア元年」企業の支援の仕方が変わった
—企業単位での支援も多かったと聞きましたがいかがでしょうか?
今回の震災では、大企業から中小企業まで、様々な企業が応援に駆けつけてくれました。メディア等でも「企業ボランティア元年」と言われていましたね。
ー私もよく耳にしました。
企業の支援は、最初は「人、モノ、カネ」が中心でした。企業のCSR部門ではそれらの支援先を求めていたので、地元はただ来てもらって、感謝の気持ちを伝えて、満足して帰ってもらえばよかった。それがwin-winの形だったのです。すると次のフェーズとして、企業が地元の行政や事業者と結びついて、ビジネス上の取引としてのwin-winの関係が出てきます。さらに次には、時間はかかるけれども、企業の持つ様々なノウハウを町づくりに活かしていく。被災地でも、被災していない地域でも生かせるシステム作りをしていって、それが、企業のネームバリューの向上にもなるし、社員の成長にもつながる。これが今目指しているwin-winです。
ーなるほど。
その間、企業さんも何度も被災地に足を運ぶことによって、今まで交流のない部署で交流が生まれたりとか、企業内で良い影響が出てくることがわかりました。支援されてばかりでない、企業にも成果をもたらすことができるのです。両者にとってメリットがあるからこそ、緊急時だけではない、継続して何度も訪れてもらえる関係性ができると考えています。

「支援」から「協働」、そして「交流」へ
—南三陸のボラセンは、常に開いている印象がありましたがいかがでしょうか?
うちのボラセンは、いつ来てもニーズはある。個人はいつ来てもウェルカム、団体は事前に言ってから来てね、という形にしました。ボランティア保険なんかも、赤い羽根共同募金からの支援でまかなうことができました。そうやって窓口を広くして体制を整えていると、リピーターが増えてきたり、あそこのボラセンはいつ行っても対応がいいというのがボランティア同士の横のつながりで拡散されて、それでボランティアが増えていきました。
—どれくらいの方が利用されたのですか?
うちの窓口を通った人だけでも、2016年3月までで、延べ15万1千人ものボランティアが、この町を訪れています。NGOさんやNPOさんを通じて直接入ってきた人たちを含めると、20万人以上と言っても過言ではないでしょう。町内飲食店や物販関係にはかなり多くの経済効果を生み出したと言えると思います。そして、いよいよボラセンのテントを閉じなければいけないという時に、町長が「感謝のつどいをやりましょう」とおっしゃったんですね。
—ボランティアの方を改めて感謝をするイベントですか?
2015年の3月に開催したこのイベントには、1100名のボランティアが集結しました。さらに、せっかくこれだけの応援もらったんだから、これを未来に繋げなきゃないだろうと町長が発案して始まったのが、「南三陸応縁団」です。

一個のおにぎりを分かちあった頃の思い
―これまで、衣食住の支援、産業支援そしてより交流に近い支援と、復興のフェーズによって様々な役割を担ってきたボラセンですが、その役割を「南三陸応縁団」に託し、ボランティアの受入に関しては、災害公営住宅や仮設住宅のコミュニティ支援に絞りました。これからはどのような展開を考えていますか?
これからは、外部との交流を保ちながら、より生活課題に密着した福祉のサービスの枠組み作りをしていきます。福祉というのは、介護保険を受けている人だけのものと考えられがちですが、子ども支援だってコミュニティ支援だって、みんな福祉なんです。それを住民の方々にも理解してもらって、住民参加型の枠組みをつくっていきたい。
―地域住民と地域外の共同ということですね。
あの時は、みんなが同じように流されたし、同じ状況だった。しかし、これからは違う。町の復興とともに、個人の経済格差が出てくるでしょう。その時に、一個のおにぎりを分かちあったあの時の気持ちを思い出せるかどうかだと思っています。苦しんでいる人は、自ら声はあげられない。そんなときに、回りに気付いてもらう「助けられ上手」になるためには、日頃から相手を信頼して、家族のことや経済状況など、情報を出さないといけない。そうすれば、中にはいい意味でおせっかいな人が出てくるかもしれない、それが大切。
―具体的にはどのような活動ですか?
住民ボランティアの仕組み作りをしていきます。地域の元気な高齢者が、移動支援や買い物支援を担って、地域のお年寄りを支える。自らも生きがい持って活動して、健康寿命を上げてもらう。「頼り上手」「助け上手」にならなきゃいけないと。震災によって外とのつながりは出来た。今度は、町内のつながりを強くしなきゃならない。今こそ、「オール南三陸」になることが必要なんです。
―「オール南三陸」の一枚岩で地域の未来を作っていきたいですね。本日は貴重なお話ありがとうございました。

ボラセンの南三陸モデル
この5年間で、南三陸の災害ボランティアセンターは他に類を見ないボラセンに成長しました。東日本大震災以降も、毎年のように災害が起き、その度ごとに日本中からボランティアが集結するようになりました。いかにしてボランティアや支援の力を生かすか、というのも、復旧復興の一つの鍵となるのは間違いないと思います。このボラセンの「南三陸モデル」が残した事例の意味というのは大きいのではないでしょうか。